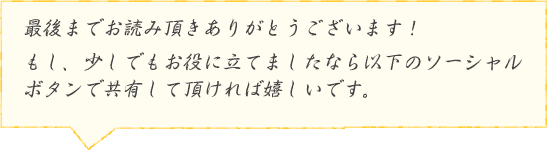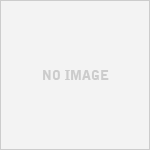大豆レシチンの概要
大豆レシチンに代表されるレシチンは、リン(グリセリン)脂質の一種で、「ホスフアチジルコリン」とも呼ばれる。細胞膜など生体膜を形成する主要成分だ。
また、脳、神経、細胞間の情報伝達物質として各々の機能調節をつかさどるほか、肝臓の代謝活動にも深く関わる。
大豆レシチンの働きについて、まずその分子構造をみてみよう。
大豆レシチンはリン酸、グリセリン、脂肪酸、コリンで構成される。リン酸とコリンの部分は水に溶けやすい(水の分子と結びつきやすい)親水性であり、脂肪酸とグリセリンの部分は、親油性。脂肪の分子と結びつきやすい。
この特徴から、大豆レシチンは動脈硬化などの予防に効果的とされている。本来は溶け合わない水と脂が、大豆レシチンの介在によってよく混ざるようになるからだ。
脂が水に乳化すると、脂肪(脂質)の代謝が活発になり、その結果、コレステロールが血管壁に付着するという動脈硬化や高血圧のもととなる現象を防ぐことができるのだ。
乳化性によって脂肪の代謝を促すということは、当然、肥満の予防・解消にも有効だ。
また、大豆レシチンは脳に多く存在することから「脳の栄養素」とも呼ばれている。先に述べた情報伝達物質としての働きによって、記憶力の衰えや痴呆(血管性痴呆症、アルツハイマー病)の予防に役立つと考えられている。
このほか、大豆レシチンはビタミンAやEなど脂溶性の物質の吸収を高める。
大豆レシチンを含む食品
レシチンを多く含む食品といえば、大豆と卵黄が挙げられる。これらを食べることで食事の中から摂取するか、大豆レシチンのカプセル剤や、大豆レシチンをベースにしたサプリメントも数多く市販されているので、利用するといいだろう。
プロテインやビタミン剤をはじめとする各種の健康食品にも配合されている。
また、市販のチョコレートのパッケージ表記などで、レシチンの名を目にすることがあるはずだ。これは、レシチンが水と脂を混ざりやすくする乳化性と、潤滑性という特性をもった添加物として利用されているからである。
adsense